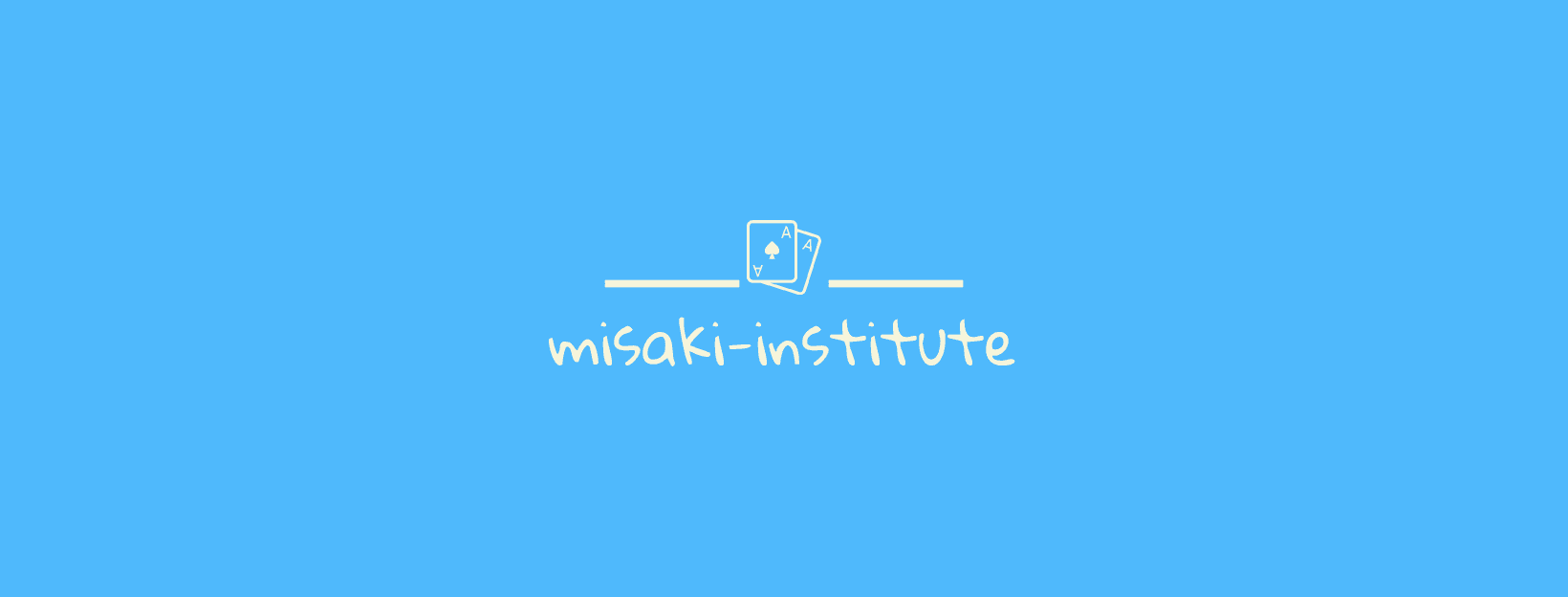求釈明ができる範囲とか
求釈明とは?
実は民事訴訟法には出てこない
いきなりですが、民事訴訟法では「求釈明」という単語は出てきません。
根拠条文
実務で「求釈明」と呼ばれているのは、民事訴訟法149条3項「当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。」という規定に基づいて、裁判長に発問を求めることを言います。
宛先は裁判長
したがって、求釈明は、相手方当事者に対してではなく、裁判長に対して行います。
範囲は無限定?
条文上は
この条文だけを見ると、当事者はどんなことについてでも裁判長に対して発問を求めることができるような気がしますし、実際、主張や証拠の提出を要求するような「求釈明」を受けることもあります(中には裁判所をすっとばして直接相手方に対して主張や証拠の提出を求めるようなものも・・・。)。
例:「Aという事実は存在するか。存在すると主張するのであれば、これを裏付ける証拠を提出されたい。また、存在しないのであれば、その理由を明らかにされたい。」
が、少しさかのぼって民事訴訟法149条1項をみると、「裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。」とされています。
結局のところ
求釈明は、同条の3項に基づいて、裁判長に対してなされるものでした。とすれば、求釈明の範囲も、裁判長が発問し、又は立証を促すことができる範囲に限られるものと考えられます。
つまり、求釈明は、訴訟関係を明瞭にするための事項(基本的には、当該当事者が主張立証責任を負う事項?)でなければならず、それを超えて相手方に主張や証拠の提出を求めることはできません。
回答義務はあるの?
条文上は?
求釈明及び一般的な回答義務はありません。
事実上は?
ただし、事実上は、回答をしないことが「弁論の全趣旨」として斟酌され、事実認定上不利に扱われてしまう可能性があります。
回答義務はないけれど
発問がなされたのであれば、裁判長にはなにかしら意図があると考えられますので、その意図を汲み取って検討する必要があります。
※その後、あまり民事訴訟法149条1項を意識せず、「訴訟上の慣行ですから」くらいの感覚で発問される裁判官もいらっしゃることがわかりましたので、よく検討して必要な範囲で回答すればいいと考えるようになりました。
書き方としては、「●は、本書面において、●の令和●年●月●日付●記載の求釈明に対し、必要と認める限度で回答する。」としたうえで、「(求釈明事項を指摘したうえで)この点については、(理由)である。したがって、当該求釈明事項については、回答の必要がないものと思料する。」、「●として求める意図が判然としないため、回答の必要がないものと思料する」などでしょうか。
変な求釈明への対抗策は?
元裁判官である門口正人先生の著書『民事裁判の要領』に、相手方に訴訟の引き延ばし等の「懸念されるような事情が感じられれば、早い段階で、相手方に対して、質問事項を書面にまとめて提出するように求めることなども考えてよいでしょう。」(110頁)という記載があり、参考になります。
ちゃんとした使い方は?
民事訴訟法149条1項にしたがって求釈明を行うとすれば、①認否等をする前に、内容をはっきりさせるとか、②主張を固定させるというくらいしか使い道はないのではないでしょうか。
なお、前述した例であれば、単に「Aという事実は存在しない」と主張して相手方の認否・反論を待てば足りますし、「被告は、Bと主張している。しかし、このような事実は存在していない。そこで、被告において、●について裏付けとなる証拠を提出されたい」というような「求釈明」についても、単にBという事実を否認すれば相手方で立証を行うでしょうから、このような求釈明は不要であるように思います。
この点、前述した『民事裁判の要領』においても、「相手方の言い分が曖昧であったり、矛盾していたりする場合で、認否をすることや反論をすることがとうていできないようなときには、曖昧な部分や矛盾する部分を問い質さざるを得ないことがあります。このような場合は、裁判所に、釈明を求めてもよいでしょうし、裁判所からも釈明があるでしょう。」(108頁)という記載があり、かなり限定的に求釈明をすることが推奨されています。
少なくとも、証拠不足を補うためにやるというのは本来の趣旨から外れているものですし、そういうことをすると手の内がバレるので、依頼者のためにもならないのではないでしょうか。
求釈明をするかどうか?
求釈明をするかどうかの判断基準としては、門口正人外著『訴訟の技能』の87頁に「まず先方主張で不明確なところをそのままにして反論してしまって大丈夫かどうかを考えます。大丈夫な場合は、そのまま決めつけてでも反論してしまう。ただ、どう考えても反論のしようがないという場合もあり、あるいは下手に反論をすると、かえって裁判所の理解が得られないこともあろうかという場合には、不明確なところを明確にするために、求釈明をすることにしております。」(87頁)という記載があるので、これを参考にさせていただいています。
以上